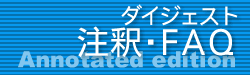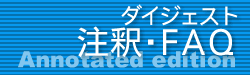|
ILTEXの貴重な導入経験から、以下に成功の6つの条件をまとめてみました。
参考にしてください。本邦初公開です。
|
| 第1章 |
パッケージの標準機能に委ねる姿勢が基本
パッケージ導入を成功させる正しい姿勢とは?
|
|
”世に例の無い”システム戦略を先駆けて構築するような場合、当然パッケージは存在しませんので、開発に頼る以外にありません。パッケージを採用するということは、”予に例のある”ものを流用するということに他なりません。企業内の業務改善を実施することは同じでも、”新規性、先駆性、独自性を問わない”、という大前提を明確にしておくことが大切です。
もちろん、パッケージの採用であっても、その標準機能の100%が流用できず、独自機能をアドオンするなどのカスタマイズも一般的ではありますが、初めから”独自要件”が前提条件になっていて、ただ単に開発コストを下げるためだけにパッケージを利用する、という姿勢は概ね失敗の元といわざるを得ません。
ILTEXの導入時例においては、開発途中で頓挫したりトラブルになった失敗事例はありませんが、白状しますと、もう少し予算が節約できたのではないかと思われるユーザー様はいらっしゃいました。代用機能やそれに近い標準機能には目もくれず、自社仕様の実現をひたすらご要求されるユーザー様でした。組織上の役割りですのでもちろん仕方の無いことなんですが、少々の違いはある代用機能を用いることのコンセンサスをもう一度社内に持ち帰って検討さえして頂ければ、おそらく不要だったと思われるカスタマイズを見積ったことがございました。
従ってまず第一に、パッケージの基本コンセプトが自社の業務要件にあっているか、標準機能が使えるのかを検討する作業が必要であり、パッケージ製品を採用するメリットとの見返りになるハードル的工数と言えます。基本コンセプトとは、「どのような規模の会社を想定し、どの部門でどのような業務に対応することを想定しているか」という基本設計思想のことです。長いこと営業していても、案外とこのことは聞かれないものです。(人目でわかる方は別です)
|
|
| 第2章 |
安定した製品を選ぶこと
実績のあるパッケージを選別すること
|
|
パッケージ製品は、運用事例が増えれば増えるほど業務対応能力の成熟度を増していくものですから、パッケージ製品だからと言って、実績のないものや、規模の大きなものはその開発ワークフローに潜む大きな危険性が解消されているとは言えないケースがありますので注意が必要です。
第1章でも述べたように”新規性、先駆性、独自性”を問わない姿勢が必要であり、実績数があり熟成した安定した製品がベストです。”新発売”はこの際、飛びつく条件ではありません。(そう言いながらILTEX製品も、”かつてない”とか”新登場”とか、逆のことを結構言ってました。リリース当時のユーザー様には筆舌に替えがたいお世話になっております。この場を借りて感謝申し上げます)
雑誌のトピック扱いで喧伝される最先端アーキテクチャーは話題にはなりますが、実際導入するとなると当然パッケージメリットはないと考えたほうがいいでしょう。雑誌に登場してから下火になって、10年経って、それでも生きているアーキテクチャーならば導入してもいいでしょう。もちろんこれはアーキテクチャーの話で製品の話ではありませんが、「10年目で導入してからさらに5年6年使用するんじゃ陳腐化じゃないの?」との声もありますが、いいえ、これが一般的なんです。
|
|
|
開発規模の大きなシステムはパッケージメリットが少ない
|
|
大きな規模の導入時例が一つだけあるような製品(パッケージとは言い難い)などの場合、この開発ワークフローの危険性が回避されているとは言えないのです。
規模が大きいシステムになればなるほど、その業務要件も多岐にわたり、全編に亘って、既存機能をそのまま流用するなどという理想が実現できないからです。
規模が大きいシステムを導入する場合は、仮に実績があったとしても、パッケージ導入のメリットの多くを期待しないことが寧ろ安全策となるでしょう。大規模開発の目安は15人月~20人月以上と考えていいでしょう。概ねその開発期間に1年相当を要する開発工程となるケースが該当します。その開発に1年相当を要するということは、パッケージがあろうがなかろうが、開発ワークフローに伝達障害が起きる可能性が高いということで、それを回避するために別の管理工数が発生してしまうのです。外注開発と考えたほうがいいでしょう。
|
|
| 第3章 |
適正な予算の組み方
導入要件と予算のバランス
|
|
第一に、何をどのくらい達成するために導入するのか、第二に何を・・・というように、達成目標がはっきりしていて、かつそれを実現するための内定予算規模が概ね適正であることが理想です。
要件が深くて、予算が少ないというケースによく失敗事例が見受けられます。インテグレーターの過度の営業努力のために、受注はしたものの、蓋を開けてみればスペック未達成というケースがまま見受けられます。そしてこのツケは、ユーザー自信に降りかかることになります。何故ならば最初からそこには機能が存在しており、それを承知で購入した責任が問われるからです。実際はインテグレーターの営業やSEの説明によって認知するわけですが、「うちの要件にあっているか?」という質問には彼らも答えられないのが普通です。最終判断はユーザーが下さなければならないのです。
|
|
|
適正予算の見分け方
|
|
しかし、この適正予算、というのが最も難しいものです。何に比べて適正か、ということになります。「今期の残り予算はこれだけだから・・・」というのも理由の一つ???うまくいけば儲けものです。
過去の事例・・・これも当てになりません、10年二昔とも言う今日、過去の事例は習うものではなく、改めるものです。
「あなたの会社の信頼できる依頼先」が見積もった料金ならまず間違いないでしょう。できれば数箇所の依頼先から回答を寄せることです。これを怠らないことは先行きに大きな違いを生じるでしょう。
そしてその回答額にそこそこ近い料金の製品が見つかれば、それが適正予算となるでしょう。”そこそこ”が大切です。大幅に有利な製品を求める、などの行過ぎた探索行為は得策ではありませんし、好機を逸します。100円均一の雑貨ではありません、少なからず技能を有するプロの手を経る製品なのですから・・・(ベンダー側の我田引水ではない積もりです)。安いなら安いで、何故安いのかをきちんと確かめてください。
|
|
|
類似した事例会社の予算を聞く
|
|
御社と同じ業態の同じような規模の企業の導入事例があればその予算を知ることも一法です。カスタマイズがない事例があればベストです。そして
|
|
|
案件の重要度を知る
|
|
次に大切なことは、その予算があなたの組織内でどのくらいの重要案件であるかということです。あなたの組織の大切な予算を割くのですから、組織における重要度が判定されているでしょう。そしてその重要度、使用可能年数の見積などによって本来選択すべき製品は絞られるものなのです。市場には沢山のパッケージ製品が出回っていますが、会社における重要度までは意識して作られていないでしょう。中には「われこそ、日本一の・・・」というすごい製品もあります。給与システムより資産管理システムに掛けた費用のほうが大きかった、などという笑えない取り違えは防ぎましょう。重要なら重要なだけ失敗回避の対策などに十分の工数と費用を見積らなければなりません。それが逆ならばそんな費用は見積もってはならないのです。
|
|
| 第4章 |
パッケージ機能を調査する
要件比較表を作成するご担当がいますか?
|
|
パッケージの標準機能がどこまでできて、何ができないか、を調査することが大切です。パッケージを購入するということは、要件→設計→開発→テストを全部端折るわけですから、要件→テストを行うわけです。ただし、事前に十分な機能テストができるケースは少ないでしょう(ILTEX製品ならば本番ライセンスに本番データを入れて評価できるうれしいサービスがありますが)。従って、要件比較表を作成して、ベンダーなりインテグレーターなりに回答させる作業になります。
これを担当するナイスマンがいればベストですが、要件比較表が細かくなりすぎないように注意してください。この時こそ導入の達成目標をしっかり見据えて、重要なものだけをアイテムとして列記するよう心がけてください。要件比較表が細かくなりすぎると、実際の調査回答にベンダーの工数が増大しますし、皆さんも検討工数が増大します。ベンダーは言われたことをやるだけでしょうが、費用や時間がかかってしまうのです。これが全く無駄な事であり、失敗の原因にもなります。
導入関係者が皆お歴々だけの場合は、ベンダーを前にして、「あれはできるかね、これはできるかね」で結構です。もちろん標準機能で、という前提つきで質問してください。
|
|
| 第5章 |
経験豊富なインテグレーターに依頼する
少予算を実現するスピード工程
|
|
経験豊富なインテグレーターなら、どの程度の要件のユーザーにはどの程度の工数で対応すればどの程度の品質が提供でき、どのくらいの利益があがる、かが解ります。ユーザーは寧ろそのスピード感覚に合わせて一緒に行動することが肝心です。最初に予想工程を要求してその説明を受けてください。工程に無理があれば必ずその段階で解るものです。
このスピード感覚こそが、少工数、少予算を実現し、導入効果も、優先順の1,2,3を確実に捕らえる結果となるのです。
|
|
|
直接インテグレーターに提案させる |
|
パッケージ製品導入のメリットは、本来の開発ワークフローのどの部分が端折れるか、にかかっているのですから。例えば、要件定義ですが、マスタをどう運用したいかを通常レビューして分析しご提案しますが、豊富な経験のあるプロならば企業規模、営業形態、経理方針、ご担当者の意向などを見て概ね推測がつきます。現状分析などは端折って、直接提案を見たほうが、適否の回答が早い訳です。
またプロなら少々の初期レビューによって概算が見えますし、導入計画が立つものです。どの要件にはどの機能が適合し、どの業務にはどの機能が適合する、と言うようにユーザーが聞かないうちから要件比較表が頭の中に出来ているものです。頼めば、即座に操作や機能を示して要件比較表を作成してくれるでしょう。それができないコンサルタントならば費用と期間ががかかってしまうことを覚悟しなければなりません。
|
|
| 第6章 |
将来性の検討
使用可能年数の見積
|
|
何年使用できれば、導入効果が達成されるかを予め見極めます。初期投資と年間継続費用を計算して、その使用可能年数における収支を総合比較して損得を判断します。
しかしながら概ねこれは”見積”によるところ大です。ILTEXの場合など、会社が小さいことから将来の計算が成り立たない、とおっしゃる向きもあります。ごもっともです。いいえ、そうでなくとも将来の約束などは誰にも出来ないのです。いっちゃなんですが、大企業ほど、その部門の採算が取れなければご存知のとおりあっという間に撤退するじゃないですか。ベンダーの大中小を問わず、当面の製品を何年使用すれば元が取れるか、という計算に如くものはありません。短期間の回収計画が一番安全です。ですからILTX製品は低価格に抑えているのです。涙、涙
|
|